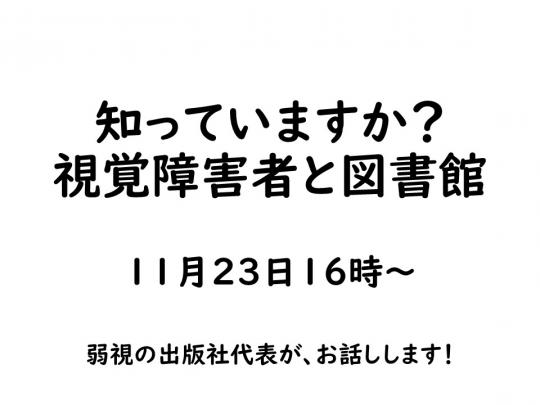New! 研究内容についての説明動画を作成しました→クリック
本研究の前提となる、視覚障害に関する解説動画はこちらになります。研究の詳しい内容は下記の報告書をご覧ください。
https://drive.google.com/file/d/1L4b7AQXU-1pDJBHfGdBT00fOWdGg1hSL/view?usp=share_link
1. はじめに
聖徳大学文学部図書館情報コース片山ゼミは、図書館情報学を専門的に学ぶなかで、SDGsにどのようにかかわられるかについて考えて活動している。今回は、
目標10「人や国の不平等をなくそう」
ターゲット10.2 年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、 全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する
に向けた取り組みのひとつとして、「公平・平等な図書館サービスの提供」を目指し、何ができるかを検討する。
1.1 研究目的
本研究では、図書館が読書推進の目的で実施する本の紹介POPに着目し、通常視覚情報を中心に構成されるPOPを健常者だけでなく視覚障害者も楽しめるものにする方法について明らかにする。
1.2 視覚障害者とは
本研究を進める上で重要である視覚障害とは『文部科学省』[1]によると、視覚障害は視機能の永続的な低下により、学習や生活に支障がある状態と定義づけされている。さらに、『やちよ障がい福祉ナビ』[2]では、その種類として以下4つに分けられると説明されている。
|
視力障害 |
視覚的な情報を全く得られない又はほとんど得られない人と、文字の拡大や視覚補助具等を使用し保有する視力を活用できる人。 |
|
視野障害 |
目を動かさないで見ることのできる範囲が狭くなる。見える部分が中心だけになって、だんだんと周囲が見えなくなる求心性視野狭窄と周囲はぼんやりえるが真ん中だけ見えない中心暗点などがある。 |
| 色覚障害 | 色を感じる眼の機能が障害により分かりづらい状態のこと。 |
| 光覚障害 | 光を感じその強さを区別する機能が、障害により調節できなくなる状態。暗順応や、明順応がうまくできない。 |
2. 先行研究と本研究の立ち位置
2.1 視覚障害者の読書についての研究
「図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務」(図書館の自由に関する宣言)としてきた図書館業界であるため、視覚障害者と図書館との関係に関する研究は数多くの研究がなされている。たとえば、著作権や各種法律、ガイドラインなどの精査し日本における制度を明らかにする研究や、各種障害者用資料に関する研究などの充実がみられる。特に昨今では、コンテンツのデジタル化や、情報ネットワーク流通を前提とした環境変化に際しての考察も充実してきている。
視覚障害者が読むということについての研究では、読みやすい文字や、識別しやすい点字についてなど、読みやすさにかかわる研究[3][4][5]や、どのように読めば効率的に読むことができるかを明らかにしようとする研究[6]などがみられる。これらの研究は視覚障害者がいかに的確にストレスなく読むことができるようになるかという観点が追究されている。
2.2 図書館におけるPOPについての研究
図書館におけるPOPに関する先行研究には、公立図書館、学校図書館、大学図書館と多様な館種についての取り組み事例の紹介がみられる[7][8]。しかし、これらは、視覚情報が中心となっていることからも「見える」ことを前提としたPOPについての研究となっている。
2.3 本研究の立ち位置
以上のように、視覚障害者と図書館サービスや、視覚障害者の読書については各種分野からの研究が進んでいる。しかし、いずれも視覚障害者と健常者、それぞれの観点からの研究にとどまっている。本研究では、年齢や障害の有無、体格、性別、国籍などにかかわらず、できるだけ多くの人にわかりやすく、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインするというユニバーサルデザインの観点に基づき、視覚障害者も健常者も同時に楽しめるPOPを考えるという点で、新規性をもつ。
2016年4月に障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が施行されたことや、2019年6月に読書バリアフリー法(正式名称「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」)が施行されたことも追い風となって、視覚障害者等の読書環境を整備する責務は社会的に認知されている。本研究では、読書環境が整備された、その次の段階ともいえる、読書をさらに充実させる方法に着目するという点で、実験的な試みとなる。このことで、今後の図書館サービス発展の一助となることを目指す。
3.研究方法
1で示した研究目的を達成するため、本研究では、POPや視覚障害に対する先行研究から学んだ留意点を反映し「みんなが楽しめるPOP」を製作し、これが実際に健常者も理解・楽しむことができるのか把握するためにアンケート調査を行う。
3.1 「みんなが楽しめるPOP」制作
3.1.1 選定した本
POPは、見える状態から、視覚的な情報を全く得られない(全盲)状態までを射程として制作した。また、POPで紹介する本[9]は、目の見えない子も見える子も一緒に喜びを共感できる作品として出版された、『これ、なあに?』(バージニア・A・イエンセン,ドーカス・W・ハラー 2007)を選定した。紹介された本が視覚障害者が楽しめなければ意味がないため、視覚情報がなくても楽しむことはできる本であることが選定理由である。
この本は、ボローニャ国際児童図書展子どもがえらぶエルバ賞、ドイツ児童文学賞、ブラティスラヴァ世界絵本原画展(BIB)特別出版賞受賞を受賞した評価の高い作品である。
3.1.2 POP制作の留意点
POP制作にあたっての留意点は、本の紹介POPや視覚障害に対する先行研究[10][11][12][13]参考にして、以下7点に設定した。
・形や触り心地を工夫し見えなくても楽しめること
・字を大きくする
・文字情報を少なくする(グラフや図を入れる
・文字フォントをゴシック体やUD体にすること
・点字・凸字を入れること
・サイズは最低A5以上
・触っても壊れない強度
今回は、見るだけでなく触って楽しんでもらうPOPを制作したため、土台は強度のある段ボールを使用した。POPサイズは書誌情報の配置や文字の大きさをふまえてA4サイズになっている。また、タイトルや作者名などの文字情報は全盲者用に点字を取り入れる他、点字を読めない人用にもわかりやすいように凸字を取り入れた。全体の構成としては、本の紹介文を入れると文字情報が多くなってしまうため、キャッチコピーと絵本中に出てくる絵を模したものが中心となっている。『これ、なあに?』は絵の部分が隆起印刷になっているため、その絵の触感に近い素材を使用しその手触りから本の内容が理解できるように工夫した。
3.2 アンケート概要
3.1で制作したPOPが健常者も楽しめるかどうかを明らかにするために、機縁法を用い、関東圏にある公立小学校の協力をえてアンケート調査を実施する。小学校の図書館に制作したPOPを一定期間設置し、実際に見る・触る体験してもらった後、Microsoft FormsによるWebアンケートに回答してもらう。
調査対象は3年生以上に限定した。これは、アンケートへの理解力や、webアンケートへの自由記述欄のタイピングができるようになっていることを配慮したためである。アンケートは事前に複数の小学校教員(聖徳大学卒業生)、および、知人の小学生のチェックをうけ、小学生3年生以上が理解できるか否か検討を行って作成した。
アンケートの質問項目は次のリンクの通りである。【アンケートへのリンク】
主な質問項目を以下に提示する。
① 学年
② 本の好悪
③ 図書館でPOPをみたか
④ POPを見て意図を読み取れたか
➄ POPをみて本への興味は湧いたか
⑥ このようなPOPを他にも見てみたいと思うか
⑦ 目をつぶって絵本の文字が読めたか
回答者の基本的な情報として、①~③について確認した。また、図書館におけるPOPの目的は、それをみた利用者が本への興味を広げたり、その本を読みたい気持ちにさせることが重要であるため、POPをみた人がそうした気持ちになれたのか否かを把握する質問を設けた(④➄)。また、POPを見た人、みていない人への共通質問として、こうしたPOPが魅力的にうつるのかを確認するために⑥を用意した。この質問の際、見ていない人がこたえられるよう、アンケート内に写真を掲載した。アンケート内で写真を見せることにより、そうしたPOPが魅力的にうつるのか否かを尋ねる質問を用意した。
4.結果と考察
4.1 調査概要
アンケートは、次のスケジュールで実施し、有効回答数は252件であった。
・調査方法:Microsoft FormsによるWebアンケート
・調査対象:関東圏にある公立小学校 3年生~6年生
・調査期間:ポップの展示2022年11月4日(金)~11月11日(金)
・アンケート調査:2022年11月10日(木)~11月15日(火)
・有効回答数:252(内ポップを見た人69、ポップを見ていない人183)
・回答者の学年内訳:3年生:73、4年生:57、5年生:96、6年生:26
4.2 「みんなが楽しめるPOP」の有効性
「みんなが楽しめるPOP」を見た児童が、POPの意図を理解できたか、また、紹介された本に興味をもてたかを把握するための質問に着目したい。調査結果からわかるポイントは以下の3点である。
❶「みんなが楽しめるPOP」は目が見える小学生に理解される
図書館でPOPをみた69名(27.7%)に対して行った、「『これ、なあに?』という本のどこがおすすめなのかわかりましたか?」という質問では、回答してもらったところ、「わかった」が43件、「ややわかった」が19件と合わせて全体の89.9%からポジティブな回答が得られた。学年別に確認してみると、学年があがるほど、理解が高まる傾向がある。「わからなかった」「ややわからなかった」と回答する児童は、3年生、4年生では10~15%存在するが、5年生になると5%に減り、6年生ではいなくなる。
❷「みんなが楽しめるPOP」はその本への興味を引き立てることができた
「『これ、なあに?をよみたくなりましたか?』」の質問でも「よみたくなった」が47件、「ややよみたくなった」が14件と合わせて全体の88.4%の回答でポジティブな結果を得られた。
また、本が好きか否かを問う質問と、「みんなが楽しめるPOP」を見てその本を読みたくなったか否かの質問をクロス集計したところ、本が好きな児童の方が読みたくなる割合は高かった。このことから「みんなが楽しめるPOP」は、もともと本が好きな児童により効果があると考えられる。同様に、このようなPOPをほかにもみてみたいかどうかを尋ねる質問でも、本が好きな層のほとんどが、「みんなが楽しめるPOP」への興味を示していた。
なお、図書館でPOPを見ていないと回答した184人の児童もFormsのアンケート上に写真を設置し、「写真のようなPOPを見てみたいと思いますか?」という質問に回答してもらったところ「思う」が138件と75%の回答であり、「みんなのPOP」が、比較的好意的に受け止められるということがわかる。
❸ 健常者と視覚障害者の図書の楽しみ方について課題が残る
「目をつぶって『これ、なあに?』をさわってみて文字がよめましたか?」の質問に対しては、「目をつぶってみなかった」が28件、「よめた」が22件、「よめなかった」が19件と目をつぶってみた人の中でも53.6%しか「よめた」という回答が得られなかった。このことについて、学年別に分析をしても、低学年だから読めない、高学年だから読めるといった違いは見られなかった。『これ、なあに?』は視覚情報でも楽しめる本であるため、目をつぶって理解できなかったことについて大きな問題はないが、視覚情報を介さずに、健常者と視覚障害者が、同一の本でどのような楽しみ方の共有ができるのか、今後検討の余地が残る。
5. おわりに
本研究では、通常視覚情報を中心に構成されるPOPを健常者だけでなく視覚障害者も楽しめるものにする方法について明らかにすることを目的に、視覚障害者を意識した「みんなが楽しめるPOP」を制作したうえで、それが健常者も楽しめるものになっているかを検証した。その結果、「みんなが楽しめるPOP」は小学生にも理解ができ、また、その本への興味をひきたてることがわかった。さらに、実際にPOPを見た人だけなく、POPの画像を見た人からも興味を得られることが分かった。
本研究の課題として調査対象の適切性が挙げられる。「みんなが楽しめるポップ」の有効性を検討するのであれば、視覚障害者と健常者両者に調査をしなければならないが、時間等の都合で、健常者のみにしか調査を実施することができなかった。今後は、視覚に障害を抱えた人が本研究で製作したPOPを楽しめるのかという部分を明らかにすることを最重要課題としたい。また、工夫した凸字の識字率もあまり高くなく、狙い通りの結果を得られなかったことも課題として残っている。今後は、調査対象の見直しと、他の資料などでの展開を考えていきたい。
引用・参考文献一覧
[1] “視覚障害とは”. 文部科学省. https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/mext_00801.html, (参照 2022-11-23).
[2] “視覚障害(視力障碍・視野障害・色覚障害・光覚障害)”. やちよ障がい福祉ナビ. https://www.town.ibaraki-yachiyo.lg.jp/page/page001511.html, (参照 2022-11-23).
[3]石田久之,天野和彦.視覚障害学生の読みやすい文字について.筑波技術大学テクノレポート.2009-12,17(1),p.6-10.
[4]柏倉秀克.視覚障害生徒に対する情報保障ー点字教科書の編集に着目してー利用.現代と文化:日本福祉大学研究紀要.2014-9-30,130,p.1-13.
[5]福井郁生.市販描画ソフトによる触図作成時の心得と実例集.筑波技術大学テクノレポート.2006-3,13,p.37-44.
[6]牟田口辰乙.点字読み塾読者の手の使い方に関する研究 : 軌跡による検討.障害科学研究=Japanese Journal of disability sciences / 障害科学学会編集委員会 編. 2012,36,p.81-94. https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10485409_po_ART0010092178.pdf?contentNo=1&alternativeNo=.
[7]平井むつみ.地域の課題を共有した、短期大学図書館と公共図書館との連携事業 : 「POP・本の帯コンクール」の実線.短期大学図書館研究.2019-3-25,(38),p.15-21.
[8]皆吉淳延.学校図書館を活用した上級生から下級生へ送るPOP作り.学校図書館.2017-1,(765),p.86-89.
[9] “これ、なあに?”. 偕成社. ttps://www.kaiseisha.co.jp/books/9784032261103, (参照 2022-11-23).
[10] 菅宮恵子. 色覚異常を考慮した教材資料作成演習の実践報告とその評価. 教職・学芸員過程研究. 2020-2-12, 2, p.14-23.
[11] 岡部正隆, 伊藤啓. 色盲の人にもわかるバリアフリープレゼンテーション. 総研大ジャーナル. 2002-3-29, 1, p.74-75. https://www.soken.ac.jp/file/disclosure/pr/publicity/journal/no01/pdf/15.pdf, (参照 2022-11-23).
[12] 矢田知恵, 片山峻太郎, 桜井香、三村敦美. リアル書店で販売促進用として入賞POPを使ってみた:地域と学校と図書館の連携「座間市中学校POPコンクール2018」. みんなの図書館. 2019-6, (506), p.8-21
[13] 廣松亜矢子. 特集, 広報デザインを考える: 大学図書館でPOPを作る、POPを使う. 大学の図書館. 2011-8, 30(8), p.138-140.
また、本研究と並行して、 色盲・色覚異常の存在を知ってもらうため、色盲・色覚異常についてもPOPを作成し、調査した。