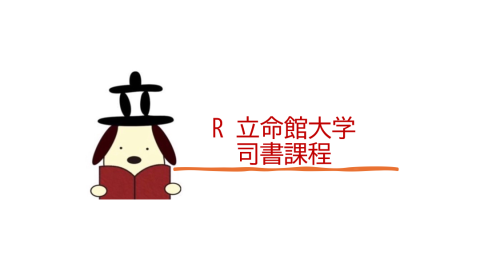立命館大学
図書館司書課程・学校図書館司書教諭課程
【課程の概要】
立命館大学図書館司書課程・学校図書館司書教諭課程は、2003年度、京都橘女子大学(現:京都橘大学)との教学連携のもとに文学部に設置されました。2009年度からはすべての科目を本学において開設しました。2013年度には、文学部生に加えて、映像学部生も履修可能となり、現在に至ります。(但し、2022年度、映像学部の教職課程の取下げに伴い、映像学部生は学校図書館司書教諭課程が履修不可となりました。)2025年3月までの本学図書館司書課程の修了者数は603名、学校図書館司書教諭課程の修了者数は132名、現在、図書館司書課程を履修している学生数は146名です。
司書課程の科目の単位はすべて卒業に必要な単位に含まれません。ですが、日本語情報学専攻の学生については、司書課程の科目が一部を除き専門科目として認定されます。(日本語情報学専攻は文学部人文学科日本文学研究学域に属し、日本語学と図書館情報学から構成されています)したがって、本稿では、図書館情報学分野の活動や学修についても一部ご紹介させていただきます。
また、本学司書課程の特色として、2013年に図書館司書の免許取得を目指して始まった文学部の自主ゼミの「立命館大学図書館研究会(りっとけん)」があります。活発な活動を継続しており、図書館に勤務する卒業生を多く輩出しています。上掲のパワーポイント資料の活動報告をご覧いただけると嬉しいです。
司書課程履修生の進路は公務員、教育、図書館、出版社、民間企業、大学院などです。図書館および図書館関連の企業に勤務する卒業生は「りっとけん」の卒業生でほぼ占められています。2025年現在の卒業生の勤務する図書館は以下の通りです。
京都大学附属図書館、大阪府立図書館、埼玉県立図書館、岐阜県立図書館、堺市立図書館、神戸市立図書館、枚方市立図書館、浦安市立図書館、草津市立図書館、三郷市立図書館、近江八幡市立図書館、栗東町立図書館、高知市立図書館、広島県立広島叡智学園中学校・高等学校学校図書館など
(卒業生からのメッセージ)
高校からの夢であった学校司書。 先進的な学びを図書館からサポートする。 | 卒業生からのメッセージ | 立命館大学文学部;図書館司書の夢を現実にするために。 学びと挑戦を続ける大学生活。 | 在学生の声 | 立命館大学文学部
【「立命館大学図書館研究会(りっとけん)」の概要】
「立命館大学図書館研究会(りっとけん)」は、2013年に図書館司書の免許取得を目指して始まった文学部の自主ゼミです。毎年、図書館総合展に出展しています。ほかにも様々な活動をおこなっています。2017年の図書館総合展のキャラクターコンテストで、りっとけんのマスコットキャラクター「りっと犬」が、応募総数74点の中から出展企業賞「ブレインテック賞」を受賞しました。
りっとけんの活動などの詳細については 上掲のパワーポイント資料の活動報告をご覧ください。もしくは下のリンクから見ることができます。
【2025年度の活動、取組、イベントなど】
① 立命館大学図書館研究会(りっとけん)の活動紹介の展示 2024年10月~2025年9月清心館1階https://www.ritsumei.ac.jp/lt/ji/news/detail.html/?id=44
立命館大学図書館研究会(りっとけん)の展示では、りっとけんの活動、図書館の意義・使命、図書館関連の書籍などについて紹介しています。なお、りっとけんのメンバーが当展示を紹介した記事が日本図書館協会図書館の自由委員会刊行の「図書館の自由」ニューズレター第128号(2025年8月)に掲載されていますので、是非ご覧ください。 図書館の自由 https://www.jla.or.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/newsletter128202508-2.pdf
上掲の立命館大学図書館研究会(りっとけん)「活動報告」(パワーポイント資料)もご参照ください。
② オープンキャンパス 2025年8月3日
立命館大学図書館研究会(りっとけん)の協力で「図書館の謎を探せ」をテーマに平井嘉一郎記念図書館でのクロスワードパズルを実施。多くの参加者にクイズをお楽しみいただきました。上掲の立命館大学図書館研究会(りっとけん)「活動報告」(パワーポイント資料)もご参照ください。
③ 「図書館サービス概論」 鎌倉幸子氏の講演 2025年12月17日(予定)
鎌倉幸子氏は東日本大震災の被災地支援での移動図書館の活動に取り組まれ、『走れ!移動図書館』を上梓されました。現在は能登半島でブックカフェを開催したり、カンボジア・ラオスの子どもたちに本を届けたり、さまざまな読書支援活動をされています。その貴重な活動と体験を伺います。
④ 図書館司書課程科目 「図書館情報資源特論」の企画展示の開催 2026年1月(予定)
選択科目「図書館情報資源特論」をご担当いただいている園田俊介氏は、その公共図書館長としての経験を踏まえ、実際に学生たちに各地域の都市空間についてその展開や特徴を調査し、そのうえで各図書館における地域資料のコレクションについて報告させています。その実践的な演習形式の授業概要と学生たちの貴重な学修成果を広く紹介するとともに、地域資料を収集・整理・発信することは、単なる情報提供の枠を超え、「課題解決型図書館」として地域社会全体の文化的持続性や共同体意識の形成を支える重要な責務であることをPRするため、本企画展示を準備しています。
⑤ 図書館インターンシップ 2025年8~9月
今年度は5名が夏季休暇の間に公共図書館でインターンシップを経験しました。学生たちは、京都市立図書館、大阪府立図書館、恵那市立図書館でお世話になり、実地でしかできない実践的な学びと経験を得ることができました。
【2024年度年度の活動、取組、イベントなど】
① 「大図研京都ワンデーセミナー」における卒論発表 2025年2月24日
大学図書館研究会の京都地域グループが「立命館大学学生による卒論発表会」を開催してくださり、図書館情報学ゼミの学生2名が卒業論文についてパワーポイント資料を使って発表をしました。
発表者1:辰己晴菜(立命館大学文学部人文学科日本文学研究学域 日本語情報学専攻 4回生、立命館大学図書 館学生ライブラリースタッフ(LS), 「立命館大学図書館研究会」メンバー) 論文タイトル:立命館大学図書館の視覚障害者等支援の現状と展望 ~学生ライブラリースタッフによるテキストデータ化サービスを中心に~
発表者2:川本かおり(立命館大学文学部人文学科日本文学研究学域 日本語情報学専攻4回生、 「立命館大学図書館研究会」前代表) 論文タイトル:コロナ禍における図書館報道 ―全国紙の図書館に関する記事を比較してー
② 「図書館サービス概論」 泉大津市立図書館シープラ」河瀬裕子館長の講演 2025年1月8日
泉大津市立図書館シープラは、いま日本で最も注目されている図書館です。画期的な取り組みを次々に生み出している河瀬館長から、その先進的、画期的な図書館サービスの実例を分かりやすく具体的に紹介していただきました。(後日、りっとけんのメンバーが実際にシープラを訪問し、河瀬館長に館内をご案内いただきました。)
③ 企画展示 「ほんものがたり-『図書館施設論』での取り組み-」 2024年10月22日~12月1日 平井嘉一郎記念図書館; 2025年1月15日~ 3月24日OICライブラリー2階展示室https://www.ritsumei.ac.jp/lib/exhibition/article/?news_id=1487
司書課程科目「図書館施設論」の担当教員である渡辺猛先生のご協力を得て企画展示を開催しました。渡辺先生は、図書館の設計にわが国で最も多く携わり、いまも現役でご活躍されている著名な建築家です。本学司書課程では2022年度から講師にお迎えし、「図書館施設論」をご担当いただいています。
渡辺先生の講義では、実際に受講学生に、対象地域や住民の「特性(個性)」や現況、展望にもとづき、建築計画および設計図を完成させるという、画期的なアクティブラーニングに取り組まれており、その授業概要や学修成果を展示・紹介しました。
さらに、多くの学生や教職員に、図書館建築デザインの背景にある理念や創意工夫の実際をご覧いただき、図書館や司書職に興味・関心を持っていただけたと思います。
④ 「図書館施設論」 特別講義:学生セミナー 2024年11月29日 平井嘉一郎記念図書館
渡辺先生の司会で、前半は履修学生のプレゼンター6名がプレゼンテーションをおこない、後半はパネルディスカッションで設計で工夫した点、苦労した点などを語り合いました。受講者34名、図書館情報学ゼミの3回生、りっとけんメンバーの他、京都市教育委員会の職員2名、佐藤総合企画の役員の方、大学図書館職員、教員など大勢ご参加くださいました。
⑤ 「図書館サービス概論」 卒業生との懇談 2024年12月11日
卒業生で現役司書の3名の卒業生の方々をお迎えし、実際に今携わっておられる図書館サービス業務について貴重な経験や知見を伺うことができました。質疑応答では盛り上がりを見せ、学生たちは一層司書の仕事に興味関心をもったようです。
⑥ 「第26回 図書館総合展」への参加 オンライン開催11月16日~24日
立命館大学図書館研究会(りっとけん)の協力によるオンライン出展で参加しました。これまでのりっとけんの活動紹介をパワーポイント資料で発表報告しました。上掲の立命館大学図書館研究会(りっとけん)「活動報告」(パワーポイント資料)をご参照ください。
⑦ 図書館インターンシップ 2024年8~9月
今年度は5名が夏季休暇の間に公共図書館でインターンシップを経験しました。学生たちは、福知山市立図書館、大阪府立図書館、姫路市立図書館、安城市立図書館、石川県立図書館でお世話になり、実地でしかできない実践的な学びと経験を得ることができました。
⑧ オープンキャンパス 2024年8月3日
立命館大学図書館研究会(りっとけん)の協力で「図書館の謎を探せ」をテーマに平井嘉一郎記念図書館でのクロスワードパズルを実施。多くの参加者にクイズをお楽しみいただきました。上掲の立命館大学図書館研究会(りっとけん)「活動報告」(パワーポイント資料)をご参照ください。
【2023年度年度の活動、取組、イベントなど】
① 図書館司書課程科目 「情報サービス演習Ⅰ」での企画展示の開催 2024年1月16日~1月30日 平井嘉一郎記念図書館
「情報サービス演習Ⅰ」は参考図書を中心に多様なメディアを使って演習に取り組んでいます。その履修生の学習成果物(参考図書の紹介ポスター、パスファインダー、レファレンス回答事例など)を展示しました。本展示を通して、司書課程の授業内容を紹介するとともに、図書館は単に本や資料を貸出すだけでなく、利用者が抱える情報ニーズや様々な課題を解決するために役立つ適切な資料・情報を提供する「情報サービス」も行っていることを多くの学生や教職員に知ってもらうことができたと思います。
② 「図書館サービス概論」 栗本正則氏の講演 2023年12月6日
栗本氏はNPOを立ち上げ大阪市内の中学校の学校図書館で居場所づくり活動をされたり、アジアのスラムや難民キャンプの子どもたちに本やランプを届けたり、さまざまな青少年支援活動をされています。困難に負けず、読書によって未来を切り開いた子どもたちの話は感動的でした。
③ 「図書館サービス概論」 大嶌薫氏の講演 2024年1月10日
国立国会図書館に長年ご勤務されていた大嶌氏から、実際に国立国会図書館のデータベースを操作しながら、幅広い先進的なデジタルサービスの概要をご紹介いただきました。また、学生に向けて採用試験とその対策などについてアドバイスをくださいました。米国留学の時のお話は特に印象に残りました。
④ 「第25回 図書館総合展」 への参加 オンライン出展10月26日~11月15日 https://www.libraryfair.jp/poster/2023/184
立命館大学図書館研究会(りっとけん)の協力によるオンライン出展で参加しました。メンバー全員の共同研究「図書館関連要素を題材にした小説作品収集と分析」についての研究成果をパワーポイント資料で発表報告しました。上掲の立命館大学図書館研究会(りっとけん)「活動報告」(パワーポイント資料)をご参照ください。
⑤ 教養教育科目連携企画 『メディアと図書館-焚書と検閲の歴史から』の展示 2023年9月1日 ~30日 平井嘉一郎記念図書館;2023年11月3日 ~12月5日OICライブラリー2階展示室 https://www.ritsumei.ac.jp/lib/exhibition/article/?news_id=1386
教養教育科目「メディアと図書館」は、文学部日本語情報学専攻、司書課程が提供しています。本科目は「図書館の歴史をたどりながら、その役割、機能、重要性について学び、大学の学びにおける図書館の活用について考えることを通して、アカデミックリテラシー(情報メディアリテラシーを含む)を身につけること」を目指しています。本展は、この講義内容の中でも第6回目の授業内容である「焚書と検閲の歴史」に焦点をあてた企画となります。
⑥ 「第75回近畿地区図書館学科協議会」 の開催 2023年9月8日 末川記念会館SK101
http://202.23.149.135/index.php?meeting75
本学司書課程が、立命館大学図書館研究会(りっとけん)の協力を得て、近畿地区図書館学科協議会を本学で開催しました。基調講演は、本学情報理工学部教授谷口忠大氏に「ビブリオバトルによる人の交流と知の循環~書籍のメディアとしての二重性~」についてお話いただきました。他大学司書課程の貴重な授業報告、実践・活動報告に続いて、本学学生たちがりっとけん共同研究「図書館関連要素を題材にした小説作品収集と分析」についての研究成果をパワーポイント資料で発表報告しました。
⑦ オープンキャンパス 2023年8月6日
立命館大学図書館研究会(りっとけん)の協力で大学図書館での 「大学図書館を楽しもう」 実施。上掲の立命館大学図書館研究会(りっとけん)「活動報告」(パワーポイント資料)をご参照ください。
以上です。ご覧いただきありがとうございました。
2022年度以前の活動についてはまた別の機会にご紹介させていただきたいと思います。
(文責 久野和子)